日本は食品ロス大国と言われていますが、その要因は何なのか、日本の食料廃棄量はどれくらいあるのか、知っておくことも大切なことです。
今の日本は、食料が足りなくて困ることはないですが、まだ食べられる食品を廃棄してしまうのはいかがなものか。
輸入に頼っている食料も多く、食料自給率が40%以下の日本は、輸入がストップしたら食料不足に陥ってしまうでしょう。
まずは家庭でできる食品ロスを減らす対策をすることを心がけることが、大事ではないでしょうか。
そこで今回は、食品ロスを減らすために、その原因や対策、家庭でできることなどをまとめて書いていきます。
PICK UP
▼食育とは!▼
食育って何をすればいいの?家庭でできることが知りたい!
食品ロスとは?

食品ロスとは、まだ食べられる食料を廃棄してしまうことです。
2015年度の日本の食料廃棄量、約2842万トンのうち、食品ロスは約646万トンもあったとのこと。
廃棄食糧のおよそ4分の1は、まだ食べられるのに捨てられたことになります。
これがどれほど大量なのか、2014年の国連・世界食糧計画での世界食糧援助量が約320万トンですから、その2倍もの食品ロスをしていることを自覚しないとです。
世界では、約8億2千万人もの人が食べ物が足りず飢餓に苦しみ、栄養不良になっていることを認識して、食品ロスを減らさないといけないですね。
食品ロスはなぜいけない?
野菜や肉、魚など、私たちの食料は地球上の生きた命です。
人間は、植物や動物の命をいただいて生命維持をしているということを思えば、まだ食べられる食品を捨てるなんてできないですよね。
食品ロスは、自然界に大きな負担をかけていることになるのです。
世界の食糧事情の改善や環境保全のためにも、ひとり一人が食品ロスを減らす努力が必要だと思います。
食品ロスの原因と対策
食品ロスの原因を知ることで、減らすための対策もできます。
食品ロスの原因
食品を捨てるのはどんなときでしょう。
- 鮮度が落ちた
- 腐敗した
- 賞味期限が切れた
- 食べきれなかった
などが挙げられますね。
腐敗してしまった食品はさすがに食べられないですが、鮮度が落ちた程度ならまだ食べられる食品も多いです。
賞味期限は、美味しく食べられるかどうかの期限なので、賞味期限切れでも食べられる期間があります。
鮮度に対して過剰すぎる意識があることも食品ロスが多い原因ですね。
料理を多く作りすぎた、食事を食べない人がいた、頂き物が食べきれなかった、外食で注文しすぎた、などで食べきれず食品ロスをだしてしまうこともあります。
食品ロスの対策
鮮度が落ちたことが気になるなら、鮮度が落ちるまでに食べきれるように買いすぎない事、食べきれないものは鮮度が落ちないうちに適切な保存をすることです。
食品ごとに、どの程度までなら食べられるか知っておくことも必要ですね。
食事の適量を知って、作りすぎない事、注文しすぎないことで食べ残しをなくすこと。
やむを得ず食べ残した時は、保存できるものは保存して次回に食べきることです。
食品ロスを減らすために家庭でできること

ほんのちょっとでも、ひとり一人が意識するだけで、日本全体の食品ロスを減らすことができます。
買い物を工夫する
計画的に買い物をすることで、食品ロスを減らすことができますね。
私も実際にやってみたところ、賞味期限切れや消費期限切れなどで廃棄する食品がなくなりました。
- ストック食材を分かりやすくする
- メニューを決めて買う物をメモする
- 買い物は数日分まとめ買いする
調味料や粉物など、常備食品を種類別に在庫が分かりやすいように保管しておくことで、不足分だけ買い足すようにします。
そうすることで、ストックがあるのに買ってしまって使い切れず捨ててしまうことがなくなります。
メニューを決めて必要な食材だけ買うようにすると、不要なものを買わずに済みますし、衝動買いもなくなります。
必要なものだけ買うので、使い切ってしまいますね。
毎日買い物に行くより、数日分まとめ買いする方が、余分なものを買わずに済みます。
私は、火曜日と金曜日の週に2回買い物に行くようにしています。
火曜日には、火・水・木の3日分のメニュー、金曜日には金・土・日・月の4日分のメニューを決めて、必要な物だけ買うようにしています。
買うものリストを持参して行くのですが、1つ2つは「あ、これも買っておこう」なんてことがあるんですよね。
なので、買い物は毎日行かない方が、余分な買い物をしなくて済むと思います。
保存方法を工夫する
旬の時期が一番おいしく価格も安くなる食材は、まとめ買いすることもありますよね。
近所の農家さんからお野菜をいただくこともあるでしょうし、家庭菜園でたくさん収穫できることもあります。
すぐに食べきれない量なら、新鮮なうちに適切な方法で保存することで、食べきる工夫をすることですね。
野菜なら、常温保存、冷蔵保存、冷凍保存と保存方法によって保存できる期間も違ってきますから、使い道によって保存方法を工夫すると良いです。
調理を工夫する
食べる人数、一人当たりの量を考えて、食べきれる量で調理すれば、食べ残しが少なくなります。
家族にお腹いっぱい食べさせてあげたいと、足りないよりは多めに作っておこうと思うこともあるかと思うんですけど、足りないくらいの方が良いかもしれません。
多めに作ると食べ残すか、食べ過ぎるかのどちらかです。
食べ残すと食品ロスになりますし、食べ過ぎると肥満や生活習慣病にも繋がりますものね。
食べ残しをなくす
食べ残しをなくすためには、食べきれる量の食事にすることですね。
腹八分目を目安に、もうちょっと欲しいくらいの食事量にしておくと、食べ残しがなくなります。
箸をつけた食品は、食べ残しても保存するのは衛生的によくないので、食べきれそうにない分は、箸をつける前に別にして保存しておくと良いです。
外食は食べきれる量にする
外食するときには、注文しすぎないことです。
食べ残ったものは、持ち帰れるなら持ち帰って食べきると良いですが、食中毒のおそれがあるなどで、持ち帰り禁止のお店も多いです。
完食してくれるお客さんの方が、お店も嬉しいはずですから、食べきれる量を注文しましょう。
食品ロスを減らすメリット
食品ロスを減らすことでどんなメリットがあるでしょうか。
少しでも廃棄食品を減らすことを意識していると、買いすぎや不要な物を買うことが減ってくるので、食費の節約につながります。
私も数日分のメニューを決めて買い物するようになってから、廃棄食品が減ったのと同時に、食費が1~2万円減りました。
毎食、食べきれる量の食事を作ることで、食べ過ぎ防止にもなっています。
地球規模で考えると、食品ロスを減らすことで、自然界の負担を減らすことができますから、環境保全にもつながります。
ひとり一人が、ほんのちょっと意識するだけで、食品ロス大国といわれている日本の現状を変えていくことができるのではないでしょうか。
まとめ
日本は食品ロス大国と言われています。
飽食時代と言われている今の日本だからこそ、世界の食糧事情の改善や環境保全のためにも食品ロスを減らすことが大切ではないでしょうか。
食品ロスを減らすために、その原因や対策、個人レベルでできることなどを知って、少しずつでも実践していくことで、現状を変えていくことができると思います。
実際に、少し意識して食品ロスを減らすことで、食費の節約にもなりました。
食品の買いすぎ、作りすぎを見直してみてはいかがでしょう。
▼こちらの記事もどうぞ▼
食べ残し問題について!なぜ食べきれないのか原因と対策!
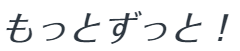



コメント