安価なときにまとめ買いして保存していた食品を、使い切れずに捨ててしまったなんてことありせん?
食品を使い切るようにすれば、食品ロスを減らすことができますよね。
そこで今回は、食品を長持ちさせて使い切ってしまうために、覚えておきたい基本的な食品保存の方法をまとめています。
どんな食品の保存方法があるの?
食品は何でも冷蔵庫に保存すれば良いというものでもないですね。
まず、どんな保存方法があるのか知っておきましょう。
常温保存
常温保存ってよく聞きますけど、どんな場所でどれくらいの温度なのでしょう。
季節によって、常温って違うんじゃないって思いません?
実は、「常温」とは「室温」のことなんです。
温度が15℃~25℃で、直射日光が当たらず多湿でない場所が、常温保存の場所になります。
夏は冷房、冬は暖房するので、常温保存の場所として適していないこともありますね。
常温保存に適しているのは、イモ類や泥つきの根菜類などです。
冷暗所保存
冷暗所は、温度が14℃以下で、日が当たらず通気性がよくて涼しい場所です。
家の中で最も涼しい場所で、台所の床下などになりますが、そんな場所がない家が多いですよね。
その場合は、野菜室で保存すると良いです。
冷蔵保存

冷蔵庫は保存場所によって温度が違うので、食品によって上手に使い分けると良いです。
冷蔵室
温度:約3~5℃
食品を一時保存したり冷やしたり、キノコ類や青菜など5℃前後の保存温度が適した食品の保存場所に適しています。
詰め込み過ぎや、ドアの開け閉めに注意して、冷蔵室の温度や節電に気をつけましょう。
冷蔵室のドアポケット
温度:約6~9℃
ドアポケットは、温度が高めで冷えにくいので、調味料や卵の保存場所に適しています。
野菜室
温度:約5~7℃
低温障害をおこしやすい野菜や果物、ドリンクなどの保存場所に適しています。
チルド室
温度:約0℃
凍らない低めの温度なので、消費期限内の肉、魚、乳製品、加工食品の保存場所に適しています。
パーシャル室
温度:約-3℃
パーシャル室は、微凍結の状態で、食品の細胞を傷めず、栄養価や美味しさをキープして保存できます。
肉、魚を約一週間、新鮮な状態で保存することができます。
低温障害
低温障害とは、0℃~4℃の低温で保存することで、変色や変質、腐敗してしまうことです。
野菜や果物には低温障害をおこすものがあります。
イモ類やきゅうり、ピーマン、なす、トマトなどの夏野菜、バナナ、マンゴー、レモンなどの果物は低温障害をおこしやすいので、常温保存か野菜室が適しています。
冷凍保存
家庭用冷蔵庫の冷凍室は約-18℃。
冷凍保存に向かない食品もありますが、冷凍保存すると長持ちしますね。
生のまま冷凍できる食品、加熱処理が必要な食品と、食品ごとに冷凍保存のコツがあります。
食品の鮮度が落ちないうちに急速冷凍すること、冷凍用保存袋に入れて空気をしっかり抜くことがポイントになります。
冷凍保存すれば数ヶ月持つのですが、美味しく食べられるのは一ヶ月程度ですね。
保存袋に冷凍した日付を入れておいて、一ヶ月以内に食べきることを基本にすると良いです。
野菜・果物の保存方法

野菜は、冷蔵庫の野菜室で保存するのが基本ですね。
イモ類や夏野菜、暑い地域が産地の果物は低温障害をおこしやすいので、常温保存か冷暗所保存にします。
使いかけの野菜は、切り口にラップをして野菜室で保存し、できるだけ早く使い切ります。
冷蔵保存すると乾燥するので、キッチンペーパーや新聞紙で包んでポリ袋に入れて保存すると良いです。
野菜は、生育中と同じ状態で保存すると長持ちするので、根の部分を下にして立てて保存すると長持ちします。
野菜ごとの保存のコツがあるのですが、基本的なことだけでも覚えておきたいですね。
鮮度維持袋を利用する
野菜専用の「鮮度維持袋」を利用すると、少しでも長持ちさせることができます。
葉物野菜など、鮮度が落ちやすいものに利用すると良いです。
ちなみに、私の個人的な実感は、ポリ袋と大差ないように感じたんですけどね。
鮮度維持袋は100均で売っているので、試してみてください。
肉類の保存方法
消費期限内に食べる予定の肉類は、ラップで空気を遮断するように包んでから密閉容器に入れて冷蔵庫で保存します。
チルド室があればチルド室が良いです。
消費期限内に食べきれない肉類は、1回分に小分けしてラップで包み、冷凍用保存袋に入れて空気を抜き、冷凍保存します。
解凍するときは、冷蔵庫に移して庫内でゆっくり解凍します。
魚類の保存方法
魚は傷みやすいので、買った日に食べきった方が良いです。
保存するときはチルド室など低温室で冷蔵保存し、翌日には食べきるように。
一尾魚を保存する場合は、エラと内臓をとってから冷蔵保存します。
魚を冷凍するときは、醤油などで下味をつけてからラップに包んで冷凍用保存袋に入れて冷凍保存します。
パックに「解凍」と表示してあるものは、冷凍すると再冷凍になるので、冷凍保存は適していません。
魚類は、保存せず食べきることを基本にした方が良いですね。
まとめ
食品を上手に保存できるようになると、腐らせてしまうことが少なくなり、食品廃棄量が減ってきます。
各家庭で少しずつでも廃棄量が減ると、日本の食品ロスも減ってくるでしょう。
ひとり一人が保存食品を腐らすことなく使い切る工夫と努力で、日本は食品ロス大国などと指摘されないようにしたいですね。
▼関連記事▼
食品ロスを減らすには!家庭でできる取り組みやメリットは?
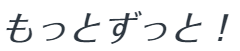



コメント